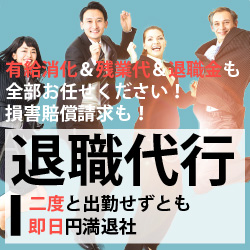労働基準監督署に相談・通報|注意点・内容・匿名タレコミは可能か等を解説

労働者が使用者との間で仕事上のトラブルを抱えていたり、違法な職場環境に耐えかねていたりする場合には、労働基準監督署に相談・通報することを検討しましょう。
しかし、初めて労働基準監督署に相談・通報を行う場合は、内容についてわからないことが多すぎて戸惑ってしまうという方も多いでしょう。
- そもそも自分が相談・通報をして良いのか
- どこの労働基準監督署に相談・通報をすれば良いのか
- 匿名でのタレコミ相談・通報はできるのか
- 相談・通報の前に準備すべきことは何か
など、労働基準監督署に相談・通報する上での基本的な知識を押さえておくと、実際に労働基準監督署へ行った際に役に立ちます。
この記事では、上記のような労働基準監督署に相談・通報する際の注意点、内容や匿名タレコミは可能か等について詳しく解説します。
目次
労働基準監督署に相談・通報すべき内容とは?
労働基準監督署の役割は、使用者が労働関係法令の内容を遵守しているかどうかの監督を行い、労働者の権利を守ることです。
そのため、労働者が使用者から自分の労働者としての権利を侵害されていると感じた場合や、職場で何らかのトラブルに巻き込まれた場合などには、労働基準監督署に相談することが一つの選択肢になります。
具体的に、どのような場合に労働基準監督署への相談・通報を行うべきかについて解説します。
使用者が労働関係法令に違反している場合
使用者が労働関係法令に違反している場合には、労働基準監督署への相談・通報を行えば、労働基準監督署が問題を認識して、会社に対する指導や処分を行ってくれる可能性があります。
労働関係法令の違反例としては、たとえば以下のようなものが挙げられます。
- 残業代の未払い
- 最低賃金法違反
- 違法な長時間労働
- 不当解雇
こうしたケースに思い当たる労働者の方は、労働基準監督署に対する相談・通報を行いましょう。
パワーハラスメント・セクシャルハラスメントなどを受けている場合
労働者が職場においてパワハラ・セクハラなどの嫌がらせを受けている場合、会社は労働者守るため、職場で行われているこれらの嫌がらせをやめさせる義務があります(安全配慮義務)。
しかし、会社がパワハラ・セクハラの事実に気づいていない場合や、気づいているにもかかわらず無視して放置している場合には、労働法上の問題が発生している状況といえます。
こうした状況に置かれている労働者が労働基準監督署に相談・通報を行えば、労働基準監督署から会社に対して。パワハラ・セクハラをやめさせるよう指導・処分が行われることが期待できます。
労災申請をしたい場合
労働基準監督署では、労災に関する事務も取り扱っています。
労働者が業務上の原因により、傷害を負ったり病気にかかったりした場合には、労働基準監督署に労災申請のやり方や手順などを相談すると良いでしょう。
労働基準監督署には誰でも相談・通報が可能
労働基準監督署は、すべての労働者の権利を守ることを目的に設置されている行政機関です。
そのため、労働基準監督署に対する相談・通報タレコミは誰でも行うことができます。
正社員に限らず派遣社員・アルバイトなども相談・通報できる
労働基準監督署への相談・通報は、会社における立場にかかわらず行うことができます。
たとえば派遣社員やアルバイトの方でも、労働基準法上の「労働者」であり、労働者としての権利が認められています。
労働基準監督署は、労働者としての権利を守るための相談・通報を常時受け付けています。
退職後の相談・通報も可能
また、労働者が会社を退職した後であっても、在職時に労働者としての権利を侵害されていた可能性がある場合には、やはり労働基準監督署に相談・通報を行いましょう。
どこの労働基準監督署に相談・通報すれば良い?管轄について
実際に労働基準監督署に相談・通報する場合、どこの労働基準監督署に行けばよいのかわからないという方も多いかと思います。
以下では、労働基準監督署の管轄を踏まえて、どこの労働基準監督署に相談・通報を行えば良いかについて解説します。
労働基準監督署の管轄は市区町村ごとに決まっている
労働基準監督署の管轄は、厚生労働省組織規則別表第四において、市区町村ごとに定められています。
この管轄に対応して、各管轄地域に一つずつ、労働基準監督署が設置されています。
労働基準監督署の「管轄」は、どの地域にある会社(事業主)に対して監督権限を行使できるかということを示しています。
労働基準監督署は、労働関係法令に違反している会社を発見した場合には、行政指導や行政処分を行います。
これらの行政指導や行政処分は、問題となっている会社の所在地を管轄する労働基準監督署によって行われることになります。
通報は会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ
会社の違法行為が明らかであり、労働者としても会社に対する処分を求めて通報を行いたいという場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ通報するようにしましょう。
会社に対して監督権限を行使できるのは、会社の所在地を管轄する労働基準監督署のみです。
そのため、管轄権を有する労働基準監督署に直接相談して、会社に対する処分の必要性を訴えましょう。
相談はケースバイケース|会社への指導・処分を求めるかどうか
一方、通報ではなく相談にとどまる場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談すべきかどうかはケースバイケースといえます。
たとえば、やや曖昧なところはあるものの、会社の違法行為が行われていることはほぼ確実で、労働者としても被害者意識を持っているというケースを考えます。
この場合は、実質的には通報に近いといえるでしょう。
このように、その後の行政指導や行政処分が具体的に視野に入っているケースでは、当初から会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談することをおすすめします。
一方、まだ問題がそこまで深刻化していないケースで、労働基準監督署に対してざっくばらんに相談したいという段階の場合には、その後必ずしも会社に対して厳しい追及が必要になるとは限りません。
この場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署ではなく、たとえば住まいの近くにある労働基準監督署に相談をしてみるのも良いでしょう。
労働基準監督署には匿名タレコミ相談・通報が可能
労働基準監督署に対して相談・通報を行った場合、会社にばれてしまうのではないかと不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、労働基準監督署には匿名タレコミでの相談・通報が可能なので、この点をそれほど心配する必要はありません。
労働基準監督署には守秘義務がある
労働基準監督署は、相談者・通報者に対する守秘義務を負っています。
そのため、労働基準監督署が会社に対して、相談・通報を行った人の情報を提供することはありません。
したがって、労働基準監督署を経由して、会社に相談・通報の事実がばれてしまうことを不安に思う必要はないでしょう。
相談・通報が会社にばれてしまう可能性は?
ただし、いくら匿名の相談であるとはいえ、労働基準監督署がその後行政指導や行政処分などに動けば、内部者による通報が行われたことが強く疑われます。
それなりに規模が大きい会社であれば、誰が通報を行ったのかを特定される可能性は低いでしょう。
しかし、小さい会社では従業員の人数が少なく、担当者も限られていて、通報された情報にアクセスできる人が特定されてしまうような場合もあります。
この場合には、匿名の通報であったとしても、会社に通報の事実がばれてしまうリスクがあるので注意が必要です。
労働基準監督署に相談・通報する際に注意すべきこと
労働基準監督署に相談・通報を行う際、事前に確認すべきことや、注意しておくべき基本的なことについて解説します。
窓口取扱時間(営業時間)をチェック
労働基準監督署は行政機関なので、窓口取扱時間は厳密に設定されています。
特に、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談をするために遠方から足を運んだとしても、窓口取扱時間外のために門前払いを食らってしまっては、無駄足になってしまいます。
そのため、事前に窓口取扱時間を確認してから、労働基準監督署を訪問するようにしましょう。
相談時の持ち物は?
相談の際の持ち物には、特に決まったものはありません。
しかし、労働基準監督署に相談をしようと思っている内容に関連する証拠や資料を持っている場合には、持参をした方が相談をスムーズに進めることができます。
たとえば、残業代の未払いを相談する場合には、残業の事実を示す証拠(タイムカードの記録など)や、給与明細などを持参すると良いでしょう。
相談前に準備すべきことは?
労働基準監督署に相談をする前には、相談内容をきちんと整理して、何が労働法上問題になっているかを説明できるようにしておくのが理想です。
労働者の方が、自分だけで法律を調べて相談の準備をするのはハードルが高いかもしれません。
その場合は、弁護士の無料法律相談を利用して、法律の専門的な観点からアドバイスを受けることをおすすめします。
電話・メールでの相談も可能
労働基準監督署では、対面での相談だけでなく、電話やメールでの相談も受け付けています。
まずはカジュアルに労働基準監督署に相談や質問をしてみたいという方は、電話相談・メール相談を利用することがおすすめです。
まとめ
労働基準監督署への相談・通報について、また内容や匿名は可能かなどについて解説しました。
労基署への相談は最初はハードルが高く感じられるかもしれません。
しかし、労働基準監督署は労働者の味方ですので、少しでも労働者としての権利が侵害されていると感じた場合には、一度労働基準監督署に相談してみることをおすすめします。
もし労働基準監督署に相談しても問題が解決しない、または会社に対してより直接的に権利を主張したいという場合には、弁護士にご相談ください。