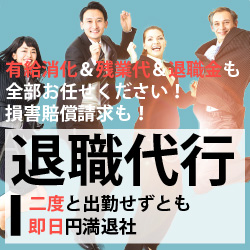パワハラ防止法とは?|罰則・事例・何が変わるか解説【2022年版】

2020年6月1日より、いわゆる「パワハラ防止法」が施行されました。
パワハラ防止法には、職場においてパワハラが発生することを防ぐために、事業主が講ずべき措置などが定められています。
現在のところ、パワハラ防止法が適用されるのは大企業のみですが、中小企業としても、将来の適用に備えて今から準備をしておきましょう。
この記事では、パワハラ防止法の内容、罰則があるか、何が変わるか、意味ないのかについて、全般的に詳しく解説します。
目次
パワハラ防止法とは?
パワハラ防止法は、労働施策総合推進法(正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)の30条の2から30条の8として、2020年6月1日から施行された法律です。
パワハラ防止法は、職場におけるいわゆるパワハラ行為を防止するための、国・事業主・労働者の責務などを定めています。
パワハラ防止法違反に罰則はある?
パワハラ防止法に定められた義務に事業主が違反した場合の罰則は、現状特に設けられていません。
しかし、事業主がパワハラ対策を怠ったがために労働者との間で紛争が発生した場合、都道府県労働局長による助言・指導・勧告の対象となる場合があります(労働施策総合推進法30条の5第1項)。
また、パワハラがまかり通っている職場であるという評判が世間に広がってしまった場合、会社としての評判はガタ落ちしてしまうでしょう。
そのため、たとえ罰則がないとしても、事業主はパワハラ防止法の規定に従って、パワハラ防止に必要な措置を講じておくべきといえます。
パワハラに該当する行為とは?
何が変わるか
パワハラ防止法では、いわゆるパワハラについての定義が設けられ「法律で明確にパワハラが禁止された」という点に重要な意義があります。
何が変わるかは、これからの人の行動次第ではありますが、法律で禁止されたことは大きなことです。
パワハラの定義と、具体的にどのような行為がパワハラに該当するのかということについて見ていきましょう。
パワハラの定義
労働施策総合推進法30条の2第1項によれば、パワハラ防止法によって防ぐべきとされるパワハラとは、以下の3つの要件をいずれも満たす言動をいいます。
①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であること
上司などによって行われる、労働者が抵抗または拒絶をしにくいであろう言動をいいます。
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
業務上必要な叱責などであればパワハラには該当しませんが、その言動が明らかに業務上必要性がない、またはその態様が不適当であるという場合には、パワハラに該当する場合があります。
③労働者の就業環境が害されること
その言動により労働者が身体的・精神的に苦痛を受け、結果として労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じるような言動をいいます。
労働者の就業環境が害されるかどうかについては、「平均的な労働者がどう感じるか」を基準に判断するものとされています。
パワハラ行為に該当するかどうかは、上記の①から③の要件を踏まえた上で、個別の事情を総合的に考慮して決定されます。
パワハラに該当する行為の事例
厚生労働省は、職場におけるパワハラの例を、代表的な類型として6つに分類しています。
(参考:「改正労働施策総合推進法等の施行によるハラスメント防止対策の強化について」)
①身体的な攻撃
暴行や傷害に当たる行為をいいます。
たとえば以下のような行為は、身体的な攻撃としてパワハラに当たります。
- 相手を殴打する行為
- 相手を足蹴りする行為
- 相手に物を投げつける行為
②精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱に当たる言動や、ひどい暴言などがこれに該当します。
たとえば以下のような行為は、精神的な攻撃としてパワハラに当たる疑いが強いといえます。
- 人格を否定するような言動
- 性的志向、性自認を侮辱する言動
- 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと
- 他の労働者の面前で威圧的な叱責を繰り返し行うこと
- 相手の能力を否定し、罵倒する内容のメールを、他の労働者にも見えるような形で送信すること
③人間関係からの切り離し
労働者を隔離したり、仲間外れにしたり、無視したりする行為をいいます。
たとえば以下のような行為は、人間関係からの切り離しとしてパワハラに当たる可能性が高いといえます。
- 労働者を仕事から外し、長期間にわたって別室で隔離したり、自宅研修させたりすること
- 労働者を同僚が集団で無視し、職場で孤立させること
④過大な要求
業務上明らかに不要なことや、労働者の能力や経験に鑑みて遂行不可能なことを強制する行為をいいます。
たとえば以下のような行為は、過大な要求としてパワハラに該当すると考えられます。
- 長期間にわたって、勤務に直接関係のない肉体労働を命ずること
- 新卒採用者に対して、必要な教育を行わないまま高すぎる業績目標を課し、達成できなかったことを厳しく叱責すること
- 業務とは関係がない私的な雑用の処理を強制すること
⑤過小な要求
業務上の合理性がないのに、労働者の能力や経験に鑑みて、あまりにも程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えなかったりする行為をいいます。
たとえば以下のような行為は、過小な要求としてパワハラに当たり得ると考えられます。
- 管理職である労働者を退職させる目的で、誰でもできる仕事を行わせること
- 嫌がらせ目的で労働者に仕事を与えないこと
⑥個の侵害
私的な事柄に過度に立ち入る行為をいいます。
たとえば以下のような行為は、個の侵害としてパワハラに該当します。
- 職場外で労働者を継続的に監視すること
- 労働者の私物の写真撮影をすること
- 労働者の個人的な情報について、労働者の了解を得ずに、他の労働者に対して暴露すること
パワハラに該当しない行為の例
逆に、パワハラには該当しない行為として、厚生労働省は以下のような具体例を挙げています。
- 労働者に誤ってぶつかること
- 遅刻などが再三注意しても改善されない場合や、重大な問題行動を行った場合に、労働者に対して一定程度強く注意すること
- 新規に採用した労働者を育成するために、短期間集中的に別室で研修などを行うこと
- 懲戒処分を行った労働者に対し、通常の業務に復帰させる前に、一時的に別室で研修を行うこと
- 労働者を育成するために、現状よりも少しレベルの高い業務を任せること
- 繁忙期であるため業務上必要であることを理由に、通常時よりも一定程度多い業務を任せること
- 労働者の能力が不足している場合に、一定程度業務の内容や量を軽減すること
- 労働者に配慮することを目的として、労働者の家族の状況などについてヒアリングすること
- 労働者の了解を得て、労働者の個人情報を必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達すること
パワハラ対策は何が変わる?事業主が講じなければならない措置とは?
パワハラ防止法において、事業主がパワハラ対策として講じなければならないとされている措置は、何が変わるのかというと、以下のとおりです。
パワハラを行ってはならないという方針の明確化およびその周知・啓発
事業主は、どのような行為がパワハラに該当するかを挙げたうえで、職場においてパワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に対して周知・啓発しなければなりません。
また、パワハラを行った者に対しては厳正に対処する旨の方針を掲げたうえで、対処の内容を就業規則などに規定し、労働者に対して周知・啓発する必要があります。
労働者の相談に応じ、適切に対応するための体制整備
事業主は、パワハラに関する労働者からの相談窓口を定め、労働者に周知しなければなりません。
相談窓口では、相談内容や状況に応じて、労働者の相談に対して適切に対応できる体制を整えておく必要があります。
パワハラ発生時の迅速かつ適切な対応
実際にパワハラが発生したという情報をつかんだ場合、事業主は事実関係を迅速かつ正確に把握する必要があります。
事実確認ができた場合には、被害者に対する配慮のための措置および行為者に対する措置を適正に行わなければなりません。
また、事実確認ができたかどうかにかかわらず、パワハラの再発防止に向けた措置を講ずべきこととされています。
その他併せて講ずべき措置
上記以外にも、事業主は以下の措置を講ずべきこととされています。
・パワハラの関係者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知すること
・パワハラの相談をしたことなどを理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
パワハラ防止には事業主・労働者がともに取り組む必要がある
パワハラ防止法では、事業主および労働者のそれぞれの責務が定められています。
事業主は、パワハラに対する労働者の関心と理解を深めるとともに、労働者が他の労働者に対する言動に注意を払うよう、研修を実施するなどの配慮をしなければなりません(労働施策総合推進法30条の3第2項)。
さらに事業主は、自らもパワハラに対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならないとされています(同条3項)。
一方、労働者としても、パワハラに対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずるパワハラ対策の措置に協力するよう努めなければならないとされています(同条4項)。
このように、パワハラ防止法は、事業主と労働者がともに協力してパワハラ対策に努めなければならないことを定めています。
【義務化】中小事業主は2022年4月1日から適用・義務化
パワハラ防止法は2020年6月1日から施行されましたが、事業主の義務に関する規定は、現状大企業のみに適用されることとされています。
一方、中小企業主については、パワハラ防止法は2022年4月1日から全面適用されます。
中小事業主の定義
中小事業主に該当するかどうかは、以下の3つの要素によって判断されます。
- 営んでいる事業の業種
- 資本金または出資の総額
- 常時使用する従業員の数
具体的には、下記の表に記載された業種に応じて、
- ①資本金または出資の総額
- ②常時使用する従業員の数
のいずれかを満たす場合、中小企業主に該当します。
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
| 小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
現在は努力義務|適用・義務化に向けた早めの対策を
中小事業主にとっては、2022年4月1日のパワハラ防止法全面適用までの間、パワハラ防止措置を講じることは努力義務にとどまるとされています。
しかし、中小事業主に対してパワハラ防止法の全面適用が猶予されているのは、その間にパワハラ防止の対策を適切に整えることができるよう、準備の期間を与えるという意味があります。
パワハラに対する世間の風当たりは、今後ますます強まることが予想されます。
そのため、小事業主としても、猶予期間の間にパワハラ防止体制の整備を完了できるよう、計画的に準備を進めていきましょう。
公務員のパワハラ対策は人事院規則で規定
パワハラ防止法は、労働施策総合推進法という、事業主・労働者間の関係を規律するための法律の一部となっています。
たとえば公務員は、事業主に雇われているわけではなく、国や地方公共団体の職員であるため、パワハラ防止法の適用対象ではありません。
しかし、パワハラ防止法の施行に合わせて、公務員についてもパワハラ防止を徹底するため、「人事院規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)」が2020年6月1日より施行されています。
同規則5条1項では、「職員は、パワー・ハラスメントをしてはならない。」と明確にパワハラを禁止しています。
その他にも、各省各庁の長に対してパワハラ防止に関する対応を義務付けるなど、パワハラ防止法の規定と同等のパワハラ対策が講じられるような内容が規定されています。
まとめ
パワハラ防止法の内容と何が変わるか、罰則、事例などを解説しました。
ハラスメント問題は、事業主にとってますます重要な解決課題となってきています。
中小事業主の方を含めて、今回のパワハラ防止法の施行をきっかけとして、職場からパワハラを一掃できるように努め、職場・会社の魅力を高めていきましょう。
具体的なパワハラ対策に関するアドバイスをお求めの際には、弁護士にご相談ください。